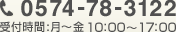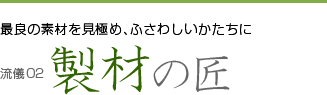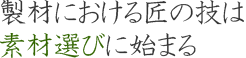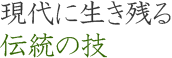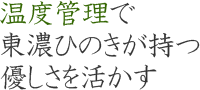木の家 匠の流儀
切り出された丸太を加工し、素材力を活かしたふさわしいかたちに整えていく。機械化が進む現代社会において、今なお東白川村が守り続ける伝統の製材技術に迫る。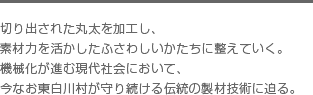



「製材」とは、丸太を加工して材として整えることを指し、その技は、素材の良し悪しを見極めることから始まる。製材には、木の節が出ないようにミリ単位で慎重に面を削り出す繊細さはもちろん、丸太の段階で綺麗に取れる面の数を見越して値段を付ける、という仕入れの技も求められるのである。
太い丸太で、小さく削っても節が出ない木を「懐が深い」と呼び、それを求めて匠の視線は丸太の皮と小口(断面)に注がれる。天然木の場合は年輪の中心がぎゅっと締まっているものがいいとされる。これは小さいうちに陽光が当たらず、何とか生き伸びるために極力自分に枝を付けてこなかったもの。よって節は少なく、年輪は成長幅が狭く密度が高い。
対して植林された人工木は、枝打ちの跡が芯に近いものが良いとされる。理想はビール瓶ほどのサイズで打たれていること。時期が遅いほど枝打ちの跡が丸太の外側に近くなり、削り出した時に節が出てしまう確率が高くなるのだ。
このように成長過程が異なる木と向き合う時には、製材後の姿に思いを馳せながら、匠は素材力を見極めるのである。
次に良質な素材を整えていく。木を一本一本を丹念に見ながら、その素質を引き出すように加工していく。現在、主流となりつつあるのは無人の機械で、5つのセンサーで木の中心を割り出し、柱の真ん中に芯がくるように削り出していく。この機械の導入により作業効率は格段に良くなったが、これだけでは綺麗な面を狙うことは難しい。

特に、根元に近い「元木」と呼ばれる部分は、斜面に立って自分を支えるために芯が山側にずれていることが多いため、削る作業自体は機械に委ねるが、どの面をどれくらい削るか、そのさじ加減は匠の手に託される。匠は「ここを削れば色や艶、柄がこうなる」と想像しながら削っていく。もし思い通りに仕上がらなければ、木の生い立ちを思い返しながら何が違っていたのか考える。
こうして匠としての感性を磨くことで、製材技術だけでなく、素材選びの技もおのずと磨かれていくのである。




製材された木は、その木が持つ優しさや美しさ、個性が引き立つ処理が施されている。
愛情込めて整えられた木。それを次の匠に託すとき、製材の匠が願うのは、木柄が活きる使われ方がされること。家の中で一番目立つ場所であったり、住む人の目にいつも優しく映り込む場所であったりと、それぞれの木の魅力が活かされ住む人が喜ぶように、そんな気持ちでものづくりが受け継がれていくことを、製材の匠は期待しているのである。